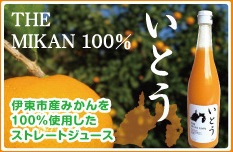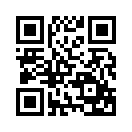2016年08月29日
日本のコロッケのルーツを探る
こんにちは。
ヒグラシの鳴き声に夏の終わりを感じてちょっぴり物悲しい今日この頃、
皆さんお元気ですか?コロッケ・メンチカツ・人参ジュースのお取り寄せ専門店
東平屋 かつお です。(www.tohei-ya.com)

最近中国でみしまコロッケを販売していて、いろいろな方から聞かれるのが、コロッケって海外にもあるの?という質問です。
そこで改めて、日本のコロッケの歴史を調べてみました。
≪コロッケの歴史≫
〇 ジャガイモをベースとしたコロッケはヨーロッパ各国にみられる古典的な付け合せ料理で、その起源は定かではありません。
明治時代、文明開化とともに急速に西洋文化が日本に流入、その中でコロッケの情報も伝わりました。コロッケの語源はフランス料理のクロケットcroquette(ホワイトソースがベースで、いわゆるクリームコロッケ)というのが定説です。しかし、コロッケの作り方がどこの国から伝わったかにはフランス、オランダ、ポルトガルなど諸説あります。その一つはクロケットを日本人好みのジャガイモのコロッケに作り替えたというものです。
ただし、ジャガイモのコロッケは冒頭に記したとおり、もともとヨーロッパ諸国にありました。フランスのクロケットも、ホワイトソースにパン粉をつける(日本のクリームコロッケ)タイプの他に、ジャガイモを使ったものもあったそうです。イギリス、オランダ、ポルトガルにも昔からジャガイモを使ったコロッケがありました。
〇 年代順に詳しく見てみましょう。
1854年(安政元年) 日米和親条約が締結されました。欧米各国との国交が開始され、西洋の食文化が流入し始めます。
幕末の開国~明治維新期 箱館・横浜・長崎などに西洋料理屋ができます。
1871年(明治4年) 1200年の肉食禁止令に終止符が打たれ、改めて肉食再開宣言がなされました。このころ文明開化が一気に進みました。
1872年(明治5年) 「西洋料理指南」にコロッケの作り方が紹介されました。ただし、まだコロッケの名前はありませんでした。
1887年(明治20年) 「日本西洋支那三風料理滋味之饗奏」にコロッケという名前が初めて登場します。
明治20年代 西洋料理法を表題とする料理本が版を重ねます。
1895年(明治28年) 女性誌「女鑑」に、クロケットとコロッケはもはや別の料理と記載されました。
1917年~1918年(大正6年~7年) 「コロッケの唄」が大流行し、庶民には縁遠かったコロッケの名前が日本中に広まりました。 (ワイフ貰って嬉しかったが、いつも出てくるおかずはコロッケ という歌詞)
大正期~昭和初期 財閥や銀行などが急成長し、サラリーマンを中心とした市民階級などに和洋折衷料理である、カレー、コロッケ、トンカツなどの三大洋食が流行します。
最初に売り出されたのは、大阪の肉屋、銀座の資生堂パーラーなど諸説があります。
〇 ヨーロッパから伝来し、日本独自に発達したコロッケですが、近年、日本のコロッケやカツに使われているパン粉は西洋のものとは異なります。日本のパン粉は「生パン粉」という大粒にちぎったようなもの。これに対して、西洋のパン粉は、パンを乾燥させて細かく砕いたもので、ドライパン粉と呼ばれています。
以上、日本のコロッケの歴史でした。
世界のコロッケの歴史については、まだまだ調査の余地がありそうです。
明治~昭和初期のノスタルジックな時代に思いをはせながら、コロッケを食べてみるのもいいかもしれません。
高級な三島馬鈴薯を使った「みしまコロッケ」について、くわしくはこちらから→

ヒグラシの鳴き声に夏の終わりを感じてちょっぴり物悲しい今日この頃、
皆さんお元気ですか?コロッケ・メンチカツ・人参ジュースのお取り寄せ専門店
東平屋 かつお です。(www.tohei-ya.com)
最近中国でみしまコロッケを販売していて、いろいろな方から聞かれるのが、コロッケって海外にもあるの?という質問です。
そこで改めて、日本のコロッケの歴史を調べてみました。
≪コロッケの歴史≫
〇 ジャガイモをベースとしたコロッケはヨーロッパ各国にみられる古典的な付け合せ料理で、その起源は定かではありません。
明治時代、文明開化とともに急速に西洋文化が日本に流入、その中でコロッケの情報も伝わりました。コロッケの語源はフランス料理のクロケットcroquette(ホワイトソースがベースで、いわゆるクリームコロッケ)というのが定説です。しかし、コロッケの作り方がどこの国から伝わったかにはフランス、オランダ、ポルトガルなど諸説あります。その一つはクロケットを日本人好みのジャガイモのコロッケに作り替えたというものです。
ただし、ジャガイモのコロッケは冒頭に記したとおり、もともとヨーロッパ諸国にありました。フランスのクロケットも、ホワイトソースにパン粉をつける(日本のクリームコロッケ)タイプの他に、ジャガイモを使ったものもあったそうです。イギリス、オランダ、ポルトガルにも昔からジャガイモを使ったコロッケがありました。
〇 年代順に詳しく見てみましょう。
1854年(安政元年) 日米和親条約が締結されました。欧米各国との国交が開始され、西洋の食文化が流入し始めます。
幕末の開国~明治維新期 箱館・横浜・長崎などに西洋料理屋ができます。
1871年(明治4年) 1200年の肉食禁止令に終止符が打たれ、改めて肉食再開宣言がなされました。このころ文明開化が一気に進みました。
1872年(明治5年) 「西洋料理指南」にコロッケの作り方が紹介されました。ただし、まだコロッケの名前はありませんでした。
1887年(明治20年) 「日本西洋支那三風料理滋味之饗奏」にコロッケという名前が初めて登場します。
明治20年代 西洋料理法を表題とする料理本が版を重ねます。
1895年(明治28年) 女性誌「女鑑」に、クロケットとコロッケはもはや別の料理と記載されました。
1917年~1918年(大正6年~7年) 「コロッケの唄」が大流行し、庶民には縁遠かったコロッケの名前が日本中に広まりました。 (ワイフ貰って嬉しかったが、いつも出てくるおかずはコロッケ という歌詞)
大正期~昭和初期 財閥や銀行などが急成長し、サラリーマンを中心とした市民階級などに和洋折衷料理である、カレー、コロッケ、トンカツなどの三大洋食が流行します。
最初に売り出されたのは、大阪の肉屋、銀座の資生堂パーラーなど諸説があります。
〇 ヨーロッパから伝来し、日本独自に発達したコロッケですが、近年、日本のコロッケやカツに使われているパン粉は西洋のものとは異なります。日本のパン粉は「生パン粉」という大粒にちぎったようなもの。これに対して、西洋のパン粉は、パンを乾燥させて細かく砕いたもので、ドライパン粉と呼ばれています。
以上、日本のコロッケの歴史でした。
世界のコロッケの歴史については、まだまだ調査の余地がありそうです。
明治~昭和初期のノスタルジックな時代に思いをはせながら、コロッケを食べてみるのもいいかもしれません。
高級な三島馬鈴薯を使った「みしまコロッケ」について、くわしくはこちらから→